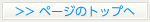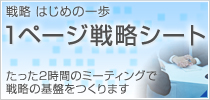- このページの要点
-
- T段階での主な失敗は、「従業員に戦略が十分に伝わっていないこと」
- 戦略の策定者(経営陣)と実施者(従業員)が異なるため、あらゆる手段を用いて戦略をしっかりと伝達することが重要
- 戦略の伝達は、研修として実施し、受講者の理解度を確認しながら進めることが必要
- 研修の効果は、カークパトリックの第2段階までに限定することが現実的
T段階での失敗
戦略策定段階(S)をクリアして一貫性のある戦略が策定できたとしても、戦略が実行されるためには、まだまだハードルがあります。
まず考慮しなければならないのは、戦略を実施する主体は、主に従業員であるということです。
戦略や計画を実行する際、よくPDCA(Plan・Do・Check・Action)やPDS(Plan・Do・See)と言われるように「Plan(戦略実行4STEPではS段階)」のあとにすぐ「Do(E段階)」が来ますが、企業戦略の場合は、戦略の策定者(経営陣など)と実施者(従業員など)が異なることが多いため、戦略を伝達する段階(T段階)を無視することはできません。
従業員のみなさんは目の前に解決しなければいけない仕事を抱えているのが普通でしょう。明日までに完了しなければならない仕事があるのに、会社の戦略のことを考えろというのは、酷とも言えます。
だからと言って、従業員は戦略に関して無頓着でよいわけではありません。本来、目の前にある日常業務というものは、戦略の実施そのものですので、当然、従業員は戦略についてよく知っておく必要があります。
ステップ社のケース(対策前)
架空の旅行会社ステップ社では、戦略策定が完了したようですが、その後、社員はなんと言っているか聞いてみます。
| 佐々木社長 | おかげさまで戦略をしっかり作れたので、全社員を集めて研修を行ったよ。みんな納得してくれたようだった。 |
|---|---|
| (商品企画部) 香川さん |
我が社の戦略? そういえばなんか研修があって冊子が配られましたかね。なくしてしまいました・・・ |
| (研修担当) 宮間さん |
ふうう、やっと、社長がやりたがっていた戦略研修が終わったわ。さて、戦略研修で時間をとられてしまったけれど、そろそろ今年度の研修テーマを考えないと。 |
T段階における主な失敗
(1)従業員に戦略が十分に伝わっていない
社長は戦略についてよく考えているかもしれませんが、社員には目の前の業務があり、通常はあまり戦略など意識していないはずです。その中で1回話しただけでは、不十分でしょう。そんな話があったことすら忘れている社員がいても不思議ではありません。
一方、いったん「戦略」から離れて、研修担当の宮間さんの話を詳しく聞いてみると、
- 研修の効果ってどう説明すればよいのかしら
- 研修のときは理解してもらえても、職場に戻ると研修内容が活かされていないことが多いみたい
- 外部講師だと的はずれな研修になる可能性もあるけれど、内部講師の手配は難しいし
など、研修担当者としての悩みは尽きないようです。
(2)戦略の内容と伝達対象者にずれ
たとえば、現場の営業担当者に、M&A戦略の話をしてもあまり意味はないでしょう。対象範囲がM&A戦略といった全社的な話であれば、それを伝える対象者は、M&A施策の実行に携わる人にするべきでしょう。各自の業務内容にあったレベルの戦略を伝えるべきでしょう。
対策
対策1:戦略を伝え、現場と共有することを軸とした研修を行う
(1)どのような研修を行うか
戦略は策定しっぱなしではなく、現場と共有してこそ初めて意味があることを認識し、現場と共有するために必要なリソースを投入するべきです。 具体的には、社内研修を実施するということになります。戦略策定主体である経営者や経営企画担当者と、現場では、経営や戦略に対する意識も基礎知識も圧倒的に違うでしょうから、あらゆる手段を使って戦略を伝えていく必要があります。 その際のポイントを、4W1Hに従って整理します。
【What(何を研修する)】
- 戦略を伝え、共有することを主軸においた研修
(戦略そのものだけでなく、その戦略に至った考え方も含む)
一般論として、物事を単体で覚えるよりも、その背景にある理論を学ぶことによって、飛躍的に定着率が高まるでしょう。「歴史上の出来事を単体で覚えるより、出来事に至った背景を知れば理解が深まる」、「数学の公式だけ覚えてもすぐ忘れるが、導出の方法をマスターしていればまず忘れない」ようなことです。
戦略を伝える場合は、「○○をしなさい」という実施内容だけでなく、戦略策定の背後にある考え方(フレームワーク)もあわせて伝えることが効果的だと考えます。
「お客さまとは誰なのか?」、「お客さまにとっての価値とは?」、「自社にはどのようなリソースがあり、何を使うのか?」、「競合とは誰なのか?」、「どのように差別化するのか?」というところまできちんと伝えることが必要です。
【Who(誰が研修する)】
- 戦略立案主体から内部講師を選出(社長がベスト)
企業のコアの部分であり、外部講師には務まりません。また、単に内容を伝えればよいというわけではなく、多分に、精神的・感情的な要素が関係してきますので、社長が自分の言葉で真摯に説明することが、最良の方法だと考えます。それだけのコストをかけても、是非、実施すべき研修ではないでしょうか。
ただし、メインの戦略研修以外に行う研修に関して、たとえば、ビジネスマナー、情報技術、財務諸表の読み方等、汎用的なものであれば、外部講師に依頼することが効率的だと考えられます。
【Where(どの手段で研修する)】
- 様々な形態での研修
(経営陣からの直接的な説明、eラーニングなどのコンテンツによる説明、日常的に使うカレンダー・手帳・社内システムのトップ画面などへの掲載や社内掲示など)
あらゆる機会を使って、戦略の共有をはかっていくことが効果的です。「経営陣による説明会」や、「理解レベルを確認するテストなどを含んだeラーニング等のコンテンツ」はもちろんのこと、日常的に使うアイテムへも組み込み、嫌でも社員の目に触れるくらい繰り返して共有をはかることが重要です。「また社長は同じことを話している」と思われるくらいになってはじめて、社員の中に定着しつつあると言えるでしょう。
【When(いつ研修する)】
- 一回研修し冊子を配ったら終わりではなく継続的に
Whereと密接に関連しますが、繰り返し継続的に共有をはかることが重要でしょう。人間は、忘却する生き物ですし、自分の仕事との関連が理解できない状況下で一回聞いた戦略など、ほぼ100%すぐに忘れるでしょう。よって、ことあるごとに繰り返し共有をはかることが重要です。
【How(どのように研修する)】
- 研修受講者の理解度を把握
(後述のとおり、戦略を理解してもらえれば、研修の効果は達成したと考える)
戦略関連用語は意味の幅が広い用語が多く、各用語の定義をしっかりとしないと、話し手と聞き手での認識のずれが発生します。たとえば、戦略、市場、ターゲット、差別化、などなど、細心の注意を払って使う必要があると思います。
現場の理解度を把握しながら、正確に戦略を伝えるためには、テストを導入することが有効です。テストというと嫌悪感を示す従業員は少なくないかもしれませんが、点数をつけるためのテストではなく、理解度にあわせた説明をするためと言えば、抵抗は和らぐかと思います。
一方、戦略関連用語を正しく認識できる土壌が整えば、戦略自体を伝えることはそれほど難しくはないと思います。一貫性のとれた戦略であれば、論理構成がしっかりしており、すっきりと理解しやすいものであることが多いからです。
(2)研修の効果
さて、研修担当の宮間さんが気にしていた研修の効果に関しては、「カークパトリックの4段階評価」が有名です。研修ご担当者様にはご存知の方も多いかと思いますが、下記の4段階で評価するもので、第1段階がクリアできて次に進み、第2段階がクリアできて・・・と段階的に進みます。
| 段階 | 代表的な評価方法 |
|---|---|
| 1.Reaction(研修満足度) | 受講直後のアンケート調査等による受講者の満足度の評価 |
| 2.Learning(学習到達度) | 筆記試験やレポート等による受講者の学習到達度の評価 |
| 3.Behavior(行動変容度) | 受講者自身へのインタビューや他者評価による行動変容の評価 |
| 4.Results(成果達成度) | 研修受講による受講者や職場の業績向上度合いの評価 |
また、ジャック・フィリップスらはこれをベースに5段階評価法を提示しています。
しかし、1(研修満足度)・2段階(学習到達度)はともかく、3段階(行動変容度)以降は急に測定や検証が難しく手間がかかるものになります。
また、いくら研修でしっかりと伝えても、実施する現場に問題があれば、社員の行動は変容しないでしょう。
ましてや4段階(成果達成度)は、策定された戦略自体の良否も大きく影響してくるので、そこまでを研修の効果に含めるのは、あまり現実的ではないですし、「どうしても研修の効果を業績と関連付けて整理しなくてはいけない」と考えることは、研修担当者のリソースの無駄遣いにもなりかねません。
そこで、戦略実行4STEPでは、カークパトリックの2段階(学習到達度)までを研修の効果として割り切り、その後3段階での行動変容については、戦略実施段階に委ねることにします。
つまり、1、2段階をT(伝達段階)の成果、3段階はE(実施段階)の成果、4段階ではS(戦略策定段階)を含めた戦略実行4STEP全体の成果と捉えます。
このように考えると、研修担当者が抱えている悩みの多くは解決されます。たとえば、「研修の効果」はカークパトリックの4段階評価のうち2段階までをカバーすれば十分なので、戦略の理解度で評価すればよいでしょう。 「職場に戻ると研修内容が活かされない」に関しては、次のE(戦略実施)段階の良否にもよりますが、日常業務に直結する研修内容のため、職場に戻ったら忘れてしまったということは大幅に減るでしょう。
ステップ社の対策
ステップ社では、以下の施策を行うこととしました。
- 全社員が一堂に会する戦略研修を海外にて実施(社員旅行を兼ねる)し、社長より戦略を周知
- 四半期ごとに社長からのメッセージをライブ配信するとともに戦略の理解度テストをeラーニングで実施
- 日常的に使用する社内システムのトップ画面にも戦略を掲示
対策後の、ステップ社の社員の声は次のとおりでした。
| 佐々木社長 | 10回言って初めて通じるのか・・・ |
|---|---|
| (商品企画部) 香川さん |
戦略なんて自分には関係ないと思っていたが、自分たち自身が戦略を実施する主役だったのか・・・ |
| (研修担当) 宮間さん |
会社の業務全体の中で、自分の仕事の意義が感じられた。戦略を現場に伝えるという重要な仕事の一端を担えてよかった。研修の効果の考え方もクリアになった。 |
| (営業部) 阪口さん |
海外で研修? すごい! |