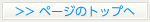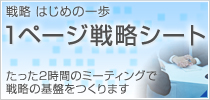- このページの要点
-
- P段階での主な失敗は、「戦略の検証ができていないこと」
- 売上 = 客数 × 客単価 =( 新規顧客数 + リピート顧客数 ) × 客単価
- 戦略指標として設定している「価値を享受して満足していただいたお客さま数」と、リピート受注との関係を把握することが効果的
- 商品に応じて対象期間を設定し、その期間内の購入をリピート受注と考えると、集計しやすい
- 戦略の成果が発現するまでには時間差が存在するので、過去を振り返ることも重要
P段階での失敗
とうとう最終段階です。戦略を実施した結果をうけて、はたしてその戦略が妥当なものであるを確認します。
一般に、企業の売上は、市場や競合などの外部環境や、自社の状況、運不運などさまざまな要素に左右されますので、戦略の成果と売上を厳密に結びつけることは困難でしょう。しかし、何も検証しなければ、戦略を評価できませんし、次にどのような戦略を打てばよいのか、再び0から考えることになります。また、「本当に戦略は実行する意味があるのか?」といった議論も出てきかねません。
そこで、この段階では、戦略指標値と売上の関係をできるだけ定量的、論理的に捉え、戦略の妥当性を検証する方法をご紹介いたします。
ステップ社のケース(対策前)
ステップ社では、各段階をクリアし、策定した戦略を具体的な行動として実施してきましたが、社長や社員はあまり納得していないようです。
| 佐々木社長 | みんながんばってくれて戦略は実施したんだけど、売上は特に変化がない。この戦略は失敗だったのではないか。 |
|---|---|
| (営業部) 長友さん |
現場がいくらがんばっても、成果が出るのは何年か先なんだよね。その時、自分はもうこの会社にいないかもしれないし。ここだけの話だけど。 |
P段階における主な失敗
(1)戦略の検証ができていない
戦略の検証は、戦略実行4STEPの中でもっとも難しい作業かもしれません。その理由として、戦略の実施と、成果(売上など)の発現の間にはタイムラグ(時間差)があることがあげられます。そのため、戦略実施の効果を的確に把握することができず、戦略が成功だったのか失敗だったのかを判断しかねるということになりがちで、こうなってしまうと、そもそも戦略なんてあってもなくても同じではないかといった意見が出てきてしまいます。
対策
対策1:戦略の妥当性を検証する
戦略が当初計画どおり実施されたとしても、まだ安心するわけにはいきません。最終目的は戦略を実施することではなく、戦略を通して売上を向上させることです。戦略は実施したけれども、思ったほど売上は上がらなかったということは当然ありえますので、戦略の妥当性、つまり、戦略指標値が改善された場合に本当に売上が向上するかを検証する必要があります。
なんらかの理由で戦略指標値が改善されず、売上も向上しなかった場合は、戦略を実施できなかったことがまずいわけで、戦略自体は妥当であるかもしれません。戦略指標値は改善されたのにもかかわらず、売上が向上しなかった場合に、戦略が妥当ではないということになります。
さて、戦略指標と売上の関係を整理します。「【STEP1】S(戦略策定)段階」の「対策2:全社横断的に適用できる戦略指標を1つ設定する」の項で、
- 「戦略に従った行動をとる」→
- 「戦略的に提供する価値をお客さまに享受していただき満足していただく」→
- 「リピートや口コミなどによって継続的な売上があがる」
ということを前提に戦略指標を考えてまいりましたが、ここで、二つ目の「→」、つまり、「価値を享受していただいた結果がどのように継続的な売上につながるか」について、もう少し考えてみます。
一般に売上は次のように分解されます。
売上 = 客数 × 客単価 =( 新規顧客数 + リピート顧客数 ) × 客単価
価値を享受して満足していただいたお客さまは、再度購入していただければリピート顧客数の増加という形で売上向上に貢献します。また、口コミをしてくれて新規顧客数の増加にも貢献してもらえる可能性があります。新規顧客数は、販促キャンペーンなどの影響を受けやすいですし、口コミを定量的に捉えることが難しい面があるので、まずは、リピート顧客数を捉えることが重要になってきます。そこで、戦略指標として設定している「価値を享受して満足していただいたお客さま数」と、リピート受注との関係を把握します。
ただし、あるお客さまが価値を享受して満足してくれてから、次の注文をするまでには、時間差(タイムラグ)があります。時間差は、たとえば、
- 日用品、飲食サービス→ 1年以内
- 雑誌年間定期購読 → 1年以内
- ホテル、旅行など → 3年以内
- 耐久財(例:自動車) → 5〜8年以内
といったように、商品・サービスによって異なります。
新規顧客数は商品が自動車の場合、6年後に購入(車種は違うにせよ)していただいた場合、リピートと考えてよいでしょうが、レストランで6年前に来たお客さまをリピート顧客と扱うのは若干不自然です。レストランにとってのリピート顧客には、1年に一回くらいはご来店いただきたいでしょう。
そこで、自社の商品・サービスに関して、リピートとみなす対象期間を設定し、その期間内に再度、購入してくれたお客さまをリピート顧客と考えると、集計しやすくなります。上記の場合、日用品や飲食サービスなら対象期間は1年、旅行会社なら3年といった形です。
そして、価値を享受して満足していただいたお客さまに関して、対象期間内に再注文があった場合はリピート受注と考えます。ある期間(月、年など)に価値を享受して満足していただいたお客さまがN人いらっしゃった場合、それから対象期間だけ経過すると、N人のうち何人がリピートしてくれたかが確定しますので、ある期間におけるリピート率が算出できます。対象期間が1年の場合、1年前に満足していただいたお客さま(の集団)のリピート率が現時点で確定するということです。
半年前に満足していただいたお客さまに関しては、まだ、リピートしていただけるかわからないので、半年前のリピート率は現時点では確定しません。対象期間が3年間だとすれば、現時点で確定しているリピート率は3年前時点のものまでとなります。
過去を振り返りすぎだというご指摘があるかもしれませんが、成果が発現するための時間差(タイムラグ)が存在することを考えれば、これは致し方がないのではないでしょうか。逆に、焦って、短期間に成果を求めようとしすぎると、戦略は適切であるにもかかわらず、「指標値は改善しているのに売上が上がらないからこの戦略は失敗だ」などと判断を誤ってしまう可能性があります。
さて、リピート率が算出できたならば、その値が悪くなっていないか、つまり、戦略指標値が改善すれば、リピート数も増えているかを確認することになります。リピート率が低下している場合は、いくら戦略指標値を改善させても、売上につながらないことになるので、戦略の見直しが必要です。
なお、一生のうちに、通常は一回程度しか購入しない商品・サービス(結婚式、マイホーム、MBA留学など)については、リピートはあまり期待できませんので、口コミや評判による新規顧客獲得に力を入れることになります。友人紹介キャンペーンなどを精力的に実施して、口コミ状況を極力定量にとらえ、戦略指標値と口コミによる受注の関係を把握するといった取り組みが重要になってきます。
ステップ社の対策
ステップ社では、リピート受注の平均的な間隔を参考に、3年間をリピート対象期間と設定し、リピート状況を把握することにしました。現時点では、戦略実施から1年程度たち、徐々にリピート受注が見受けられるようになってきたようです。最初の1年間で、戦略指標値は目標の500人を達成したので、これからのリピート受注に期待しつつ、戦略の妥当性、つまり、戦略指標値とリピート受注との関係を注視しているところです。
対策後の、ステップ社の社員の声は次のとおりでした。
| 佐々木社長 | 戦略なんてあってもなくても結局はそれ以外の要因に左右されるという思いもあったが、どこまでは検証すべきなのかがわかった。今後は、検証すべきところは検証し、戦略の精度を高めていきたい。 |
|---|---|
| (営業部) 長友さん |
自分たちのがんばった結果が、自分の評価に反映されるだけでなく、継続的な売上につながることを確認できたので、やりがいが増してきました。がんばりますよ! |
これで戦略実行4STEPのご説明は終了です。ここまでおつきあいいただきまして誠にありがとうございました。戦略実行4STEPに関するご意見・ご感想などがあれば、ぜひ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
また、株式会社ユア・ストラテジーでは、戦略実行4STEPにもとづくコンサルティングや研修サービスを展開しております。詳しくは、「コンサルティング」、および、「戦略ベース研修」をご覧下さい。