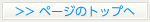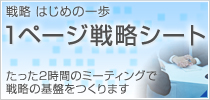- このページの要点
-
- E段階での主な失敗は、「戦略と評価制度が連動していないこと」と「戦略指標値が可視化されていないこと」
- 「戦略行動をとり戦略指標値を改善させたことを評価する」評価体系が必要
- 各部門の評価:「全社戦略指標」&「部門別条件クリア状況」による評価が有効
- 戦略指標の値をリアルタイム(日単位)でモニタリングするシステムを用意することが重要
- 日報を使い戦略指標を追求すべくマネジメントを行うと、戦略の実施が加速する
E段階での失敗
S段階(戦略策定)、T段階(戦略伝達)をクリアしたら、いよいよE段階(戦略実施)です。
ここまでの2段階がしっかりとできていれば、戦略が実施される可能性は高くなっていますが、実施する段階で失敗してはこれまでの苦労が無駄になってしまいます。
実施段階は、日常業務の中で遂行されるものですが、日常業務にはさまざまな問題がつきものであり、それらの問題に十分に配慮しないと、戦略実施の妨げになる可能性があります。
このページでは、E(戦略実施)段階における失敗とそれへの対策を整理します。
ステップ社のケース(対策前)
架空の旅行会社ステップ社における、社員の声を把握してみます。
| 佐々木社長 | 戦略もできたし、伝達にも力をいれている。指標値は改善しているかって? 管理部に集計してもらわないと今すぐにはわからないけれどみんながんばってるはずだ。 |
|---|---|
| (営業部) 長友さん |
社長の戦略の話は頭ではわかるんだけど、結局、自分たちは売上で評価されるので、現実的には難しいよ。ここだけの話だけど。 |
| (商品企画部) 香川さん |
指標値のうち自分の担当分を知りたいんだけど、どこを見ればいいんだ? |
| 本田営業部長 | ホテルは四つ星ホテルにしたいっていうお客さまに対して無理にガイド宅宿泊ツアーをおすすめして機嫌を損ねた? なんで事前に相談しないんだ! |
E段階における主な失敗
(1)戦略と評価制度が非連動
いくら社長が戦略、戦略と口うるさく言ったとしても、仮に、評価制度が戦略と連動していなければ、現場の社員が戦略を実施することはまずないでしょう。
ステップ社の例をとりますと、「現地ガイド宅での宿泊を組み込んだ、旅先により深く触れるツアー」を重点的に販売していくことが戦略で、戦略指標は「ガイドに対する満足度90%以上の旅行者数」です。それにもかかわらず、営業部員が「売上」で評価されるとしたら、営業部員はとにかく売れるものを売るでしょう。こうなってしまっては、戦略は「絵に描いたもち」になるでしょう。ですから、戦略指標を個人の評価に連動させることが不可欠です。
(2)戦略指標値が可視化されていない
多くの会社では、期間を区切って個人の目標を設定し、期末にマネジャーと面談を行い当該期間を振り返るような取り組みをされているでしょう。その際、個人の目標は戦略指標と連動させることが重要です。ただし、指標値が設定されても、たとえば、目標面談の時期になって「目標が達成できていない」と思い出したり、そもそも自分の目標がなんだったかを確認しているようでは、戦略と日常業務が完全に別物になっていると言わざるを得ません。
そのような状況下では、評価や目標管理が、ただただ手間のかかるものとしてとらえられ、「こんなことはやめたほうがよい」、「成果主義なんて日本には合わない」、などといった議論が出てきがちです。指標値は、誰もがいつでも見られるような体制を構築しておく必要があります。
(3)戦略指標値改善に向けてのマネジメント不足
全社横断的な戦略指標値があれば、各自の行動はある程度方向づけられますので、各自が勝手にばらばらな行動をとることは減少しますが、行動を完全に個人任せとしては、やはり非効率です。ステップ社では、営業部員が、戦略指標値を改善させようと思うあまり、お客さまのニーズを十分にくみとらない提案をしてしまったようです。上司などによるマネジメントがきちんと行われていれば、このような失敗は防げたと考えられます。
対策
対策1:戦略と評価制度を連動させる
(1)戦略行動をとり戦略指標値を改善させたことを評価する
戦略行動をとったかどうかは戦略実施側(現場)の責任、戦略行動をとったのに業績が向上しなかったのは戦略策定側(経営層)の責任とします。
ただし、目標以上に業績が向上した場合は、従業員にも金銭的に還元することが望ましいと考えられます。そうしないと、行動だけに注力して、最終的な結果を軽視することにもつながりかねないからです。
戦略指標値を改善させたかどうかで評価するメリットとして、「行動が売上につながるまでのタイムラグを吸収する」ということがあげられます。戦略行動を実施し、売上のための種をまいたのに、評価の直前で異動になった場合、売上だけで評価してしまうと、売上をあげるための地道な活動が評価されなくなってしまいます。戦略行動の実施と売上の間に時間差(タイムラグ)があることが評価を難しくするので、戦略行動にもとづき評価することによってその問題を軽減することができます。
(2)各部門の評価:「全社戦略指標」&「部門別条件クリア状況」による評価
各部門ともに共通の戦略指標(標準パターン:価値基準をクリアしていただいたお客さまの数)で評価することを基本とします。戦略指標値が改善すれば高い評価を得られる一方で、行動が足りずに戦略指標値が改善されなければ評価も低くなるという関係です。
しかし、全社共通の戦略指標で各部門を評価すると、仮にある部門のパフォーマンスが低く、その結果、戦略指標値が悪くなった場合に、他の部門は当然不満に思うでしょう。「営業が新規顧客を獲得しないから指標が伸びなかった」とか、「生産の不良率が高いから指標が前期より悪化した」といったことが想定されます。
そこで、各部門に対しては、戦略指標値の向上を目指しつつも、クリアすべき条件を課すことが有効です。たとえば、営業部門であれば「新規顧客を50件以上開拓する」、生産部門であれば「不良率を0.1%未満に保つ」、商品企画部門であれば「新商品のお客さま満足度80%以上」といったものです。条件をクリアした部門については、戦略指標値の良否によって評価します。基準をクリアできなかった部門については、一定のペナルティを与えざるを得ません。たとえば、戦略指標値に対して0.8掛けで評価するなどとすることによって、ある程度、部門間の公平性を保つことが可能になると考えられます。
上記をまとめると、各部門には条件をクリアしてもらう前提で、全社共通の戦略指標による評価を最優先するものです。ここで、各部門の基準を補助的・従属的な形で組み込んでいる理由は、「あくまで全社共通の戦略指標を追求することによって戦略が機能し、最終的な売上につながるはず」ということです。
たとえば、「営業部門の評価は、戦略指標への貢献が50%、部門目標としての客数向上への貢献が50%」など、補助的でない形で評価すると、場合によってはとにかく客数を増やすことに注力してしまい、結果として、せっかくの戦略が実行されない(実行され方が弱まる)恐れが出てきます。そのため、あくまでも、第一義的に目指すことは戦略指標値の改善であるということが全社に伝わる評価体系とする必要があるでしょう。
なお、各部門の役割を第一の評価基準とせず、全社共通指標を第一に使うとなると、部門間の不公平感が増すのではないかというご指摘があるかもしれません。このご指摘に対しては、若干、精神論的になってしまいますが、「それぞれが自分の役割を果たしつつ、全体として協力しあって大きな成果を目指す」という形態は日本人、日本企業には相性が良いのではないかと考え、弊社ではこの方法をおすすめしております。
(3)間接部門の評価
できれば全社に対して戦略指標を用いた評価をしたいですが、総務・経理など、業務内容を直接的に戦略指標値の向上に結びつけにくい部門は確かに存在します。このような部門では、間接的であっても、何らかの形で戦略指標との関連で評価することがよいでしょう。たとえば、採用部門であれば新入社員の戦略指標達成状況、社内システム部門であれば基準価値クリア客数一人あたりのサービス停止時間などが考えられます。
ただし、どうしても戦略指標との関連づけが難しい場合は、全社平均的な数値を使うのもやむを得ないでしょう。また、場合によっては、直接、自社の戦略遂行には関わらないのであれば、そもそもその業務を社内で行うべきかを再検討する必要があるかもしれません。
対策2:指標値がリアルタイムで確認できるモニタリングシステムを開発する
日々、戦略指標値を向上させるために業務を行い、その結果を社員の評価にも連動させるのですから、肝心の戦略指標の値をリアルタイム(日単位)でモニタリングするシステムを用意することが必要になってきます。
さて、「モニタリングシステム」とは言っても、中小規模の企業であれば、エクセルなどの表計算アプリケーションで十分に対応可能です。
「【STEP1】S(戦略策定)段階」の「対策2:全社横断的に適用できる戦略指標を1つ設定する」の項で、サービス利用者の属性・価値享受状況が把握できているかどうかを切り口として、サービスを下記のとおりA・B・Cの3タイプに分類しました。そして、戦略指標としては、各タイプの価値基準をクリアした人数を設定しています。
| タイプ | 利用者属性の把握 | 価値享受状況の把握 | サービスの例 | 価値基準のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| A:利用状況把握型 | ◯ | ◯ | 資格学校、投資信託、ソーシャルゲーム、SaaSサービス | 実際の価値享受状況 |
| B:利用者特定型 | ◯ | ✕ | ホテル、雑誌定期購読、旅行会社、会員カードのあるスーパー | 利用者アンケート(全数調査)結果で代用 |
| C:利用者不特定型 | ✕ | ✕ | 飲食店、駅の売店、スキー場 | 利用者アンケート(サンプリング調査)結果で代用 |
ということは、価値基準をクリアした人数のデータを、表示させるシステム(エクセルファイルでもよい)を作ればよいだけです。たとえば、タイプAの場合、利用者のサービス利用状況を管理しているシステムがあるでしょう。投信会社であれば当然利用者の利用状況はシステムで管理されているでしょうし、ピアノ教室であればITシステム化はされていないかもしれませんが講師のノートなどでは管理されているでしょう。
ITシステム化されていれば、それと連動して、戦略指標値をモニタリングできるシステムを構築すればよいでしょう。ITシステム化されていない場合は、新たにサービス利用管理機能を含めた戦略指標モニタリングシステムを開発してもよいですが、単に戦略指標モニタリングシステムだけを開発し、サービス利用状況は、手動で入力することにしてもよいでしょう(ただし、この場合、手動入力は徹底して行う必要があります)。
また、タイプB、Cの場合は、戦略指標としてアンケート結果を使っています。アンケートをITシステムによって実施していればそのシステムと連動すればよいですし、紙のアンケートの場合は、ピアノ教室の場合と同じように、手動で入力すればよいでしょう。
戦略指標は個人の業務や評価に結びつけますので、会社全体での指標値だけでなく、担当者ごとの指標値も集計できるような設計としておくことが重要です。 戦略指標モニタリングシステムに関しては、エクセルで始めることも可能ですが、データ管理の容易さや拡張性を考えるとアクセスなどのデータベースアプリケーションを使ったほうがよい場合もあるでしょう。また、もう少ししっかりと作り込む場合や、社外からのアクセスも想定するのであれば、WEBアプリケーションとして構築することになるでしょう。WEBアプリケーションの開発というと、費用面、労力面で大変そうですが、現在ではクラウド技術を使ったSaaS(初期投資不要で利用量に応じた課金の場合が多い)も数多く提供されており、比較的低コスト、短期間で利用を開始できますので、中小規模の会社にも使いやすい状況になってきているといえます。
対策3:日報を使い戦略指標を追求すべくマネジメントを行う
戦略指標が決まり、可視化されたら、各担当者は指標値を改善するために日常業務中で行動することになりますが、行動のやり方が悪ければ指標値は改善されないでしょう。また、適切な行動だったとしても、行動してから指標値が改善するまでには時間差(タイムラグ)があることが多いと考えられます。 1月に商品価値を向上させたとしても、お客さまに購入・利用していただくのは7月になるかもしれません。時間差があると、果たして行動が適切だったのか不安になる担当者もいると考えられます。
そこで、マネジャーである上司が、各担当者の行動を管理する(把握し、適宜、アドバイスする)ことが重要ですが、日々の行動によって指標値の改善を目指すわけですから、管理も日単位のスピードで行なっていく必要があります。月に1回や、3ヶ月に1回だけ、面談して指導もどきをするのでは、戦略実施のスピードに追いつけません。日単位で担当者を管理していくためには、日報を使うことが効果的です。
担当者は、「指標値改善に向けて当日実施した行動」、「次のアクション」、「お客さまの声とそれに対する自分の考え」などを毎日記載し、マネジャーはそれに対して適宜指導するようにします。「次のアクション」に問題があれば、マネジャーは修正指示を出すことができますし、「お客さまの声とそれに対する自分の考え」からクレームの芽が見つかることも考えられます。
なお、上では「管理」と書きましたが、これは管理であるとともに、日々の業務を通じて担当者を指導する「OJT」とも言えるでしょう。一般にOJTと言うと、指導者次第で指導の方向性がまちまちになることが多いですが、戦略指標値を改善するという明確な方向性があるため、指導者によるばらつきも少なくなることが期待できます。このため、マネジャーには、戦略内容を十分に理解しつつ、実務や指導に必要なスキルを持っていることが求められます。また、小規模な企業であれば、経営トップが直接、各社員の報告にレスポンスすることも非常に効果があると考えられます。経営トップから、戦略に基づいた指導を受けられるというのは、小規模企業ならではのメリットでしょう。
実際に日報をどのように実現するかについては、グループウェアを使ってもよいですし、単にメールのやりとりとして行なってもよいでしょう。ただし、前述の戦略指標モニタリングシステムと一体的に日報を使えるようなシステムを構築できれば、戦略指標の追求は、より効率的になると考えられます。また、T(戦略伝達)段階の施策とも関連しますが、このような日常的に利用するシステムの中(たとえばログイン画面)に、戦略の解説などを掲示し、嫌でも目に触れるような環境を構築していくことによって、戦略をより身近なものにしていくことも効果があると考えられます。
ステップ社の対策
ステップ社では、「ガイドに対する満足度90%以上の旅行者数」によって全社を評価することにしました。 その上で、営業部門がクリアすべき条件は「ホームページからの問い合わせ件数800件以上」、商品企画部門の条件は「ガイド宅宿泊つきツアーを50件以上開発」とし、それが達成できなければ評価を下げることにしました。
また、ステップ社では、売上を管理しているエクセルファイルの別シートにお客さまアンケートの結果を組み込み、「ガイドに対する満足度90%以上の旅行者数」を誰もが簡単に閲覧できるようにしました。エクセルのピボットテーブルというクロス集計機能により担当者毎の指標値も閲覧可能な状態にしました。
また、各部門内のメーリングリストを使って、「指標値改善に向けて当日実施した行動」、「次のアクション」、「お客さまの声とそれに対する私見」をマネジャーに送信し、マネジャーは毎日、確認、指導を実施するという業務フローを開始しました。
対策後の、ステップ社の社員の声は次のとおりでした。
| 佐々木社長 | いちばん大事なはずの指標値を、実際にはほとんど見ずに経営していた・・・ それにシステムと聞くと敷居が高く感じていたが、エクセルでも立派なシステムだな。 |
|---|---|
| (営業部) 長友さん |
リアルタイムで自分の指標値が見られるので、どうすれば指標値が改善されるか毎日考えるようになった。ゲーム的な感覚もあって前よりも仕事が楽しい。 |
| (商品企画部) 香川さん |
この評価制度であれば、戦略を実施することが、自分の評価に直結するので、戦略を実施したいという気持ちが高まりました。がんばりますよ! |
| 本田営業部長 | 日報を導入したので、リアルタイムで部下を指導できるようになった。やはり、私がしっかりと見てやらないと、みんなまだまだだな。 |